日本と西洋の伝統絵画にみる非言語表現の違い
- yoko97asaka
- 4月17日
- 読了時間: 6分
皆さま、こんにちは。国際ボディランゲージ協会の安積陽子です。
先日、国際ボディランゲージ協会では、「日本と西洋の伝統絵画にみる非言語表現の違い」をテーマに勉強会を開催しました。
静止画である絵画のなかに、どれだけ豊かな“身体言語(ボディランゲージ)”が存在するか――そんな問いかけから始まった今回の勉強会では、平安時代の絵巻からルネサンス期の西洋絵画まで、様々な時代と地域の作品を通じて、文化の違いとその背景を深く読み解きました。
◆ なぜ、絵画から“ボディランゲージ”を読むのか?
私は美術史の専門家ではありません。けれども、言葉にならない表現――たとえばまなざし、姿勢、沈黙の「間」――を長年読み解いてきた者として、絵画の中に描かれた身体の在り方にも、文化ごとの深いメッセージが込められていることを実感しています。日本と西洋、それぞれの絵画における人物表現を比べてみると、ただ技法が違うというだけでなく、「感情をどう表すか」「感情を表すことが是か非か」という根本的な価値観の違いが見えてきます。
◆ 「もののあはれ」と身体の言葉 ― 平安時代のやまと絵から
最初に取り上げたのは、日本美術史における代表的な絵巻物、『源氏物語絵巻』のなかの「御法」の場面でした。この場面は、病の床に伏す紫の上のために催された法会で、満開の桜の下、陵王の舞が奉納される様子が描かれます。絵の中では、紫の上と源氏がその舞を静かに見守る姿が印象的です。涙や嘆きといった直接的な表現は一切なく、人物の表情は極めて簡略化されています。しかし、そのわずかに傾けられた身体や控えめな視線、舞に対する静かな集中と、視線の向かう先の構成からは、紫の上の死を目前にした静かな覚悟と、源氏の深い想いが暗示されています。画面に漂う緊張感と静けさが、心情を間接的に伝える日本的な表現手法となっています。感情を「見せる」のではなく「漂わせる」こと。それは、日本文化における非言語コミュニケーションの核ともいえる「察し」の文化に根ざしています。
また、『源氏物語絵巻』の「東屋」の場面では、浮舟が絵を眺める姿が描かれています。表情は見えませんが、視線を落とし、袖を重ね、静かにうつむく姿からは、心の揺らぎや内面の混乱が感じ取れます。中君らが寄り添うように座ってはいるものの、正面からの視線の交差を避けている点に、日本文化における距離感の繊細さが表れています。
これは、私たちが日常で行う非言語コミュニケーションにも共通する構造であり、静けさや沈黙のなかに、最も多くの「ことば」が含まれていることを教えてくれます。
◆ 水墨画と「余白の身体」
室町時代に発展した水墨画は、人物の感情や物語を直接描写するのではなく、自然の風景や余白を通して心情をにじませる特徴があります。なかでも雪舟の作品の多くには人物こそ描かれていないものの、墨の濃淡や構図の流れによって、鑑賞者の感情を深く動かす視覚的な空間が創出されています。ここでは、身体そのものを描かずとも、山の稜線や水の流れ、空間の「間」によって、“たたずむ身体”のような存在感を漂わせています。見る者の想像力によって「そこに誰かがいる」ように感じさせる構造は、非常に日本的な非言語表現の在り方です。
つまり、ボディランゲージが姿や仕草ではなく、「空間にどう存在するか」「何を描かないか」によって語られる――それが、日本の水墨画が示すもうひとつの身体表現なのかもしれません。
◆ 「感情を演じる身体」―西洋絵画の劇場性
対照的に、西洋の絵画では、人物の感情が明確に、時に誇張される形で描かれています。
たとえば、ジョットの『キリストの哀悼』では、嘆き悲しむ聖母や使徒たちの顔に、明確な苦悩と悲しみが刻まれています。人物たちの腕の動きやうずくまる姿勢もまた、絶望の深さを象徴しており、観る者に感情的共鳴をもたらします。『リザードに噛まれた少年』では、少年が驚きと痛みに満ちた一瞬の身体反応を全身で表現しています。肩をすくめ、口を開き、目を見開いたその姿は、まさに「叫ぶ身体」。感情の爆発的な瞬間が強烈に描かれています。
背景の暗さと明暗の対比も、感情を強調し、ボディランゲージを視覚的に際立たせる構成になっています。
レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』では、キリストの「この中に裏切り者がいる」という言葉に対し、弟子たちが驚く様子などがそれぞれ異なる身振りと表情で表現しています。ある者は手を広げながら「一体誰が裏切り者か?」と驚き、またある者はキリストに「裏切り者とは自分のことか」と必死で問いています。このように一枚の絵の中で人物ごとの個性と感情反応を巧みに描き分ける手法は、まさにルネサンス的人文主義の産物ともいえるでしょう。

◆ 日本と西洋の非言語表現を比べてみて
絵画は、その時代や文化を映し出す鏡であると同時に、ボディランゲージを学ぶうえで貴重な教材でもあります。西洋の絵画では、感情を率直に表現することが重視され、怒りや悲しみといった感情も、手の動きや顔の表情、身体のひねりなどを通じて、外へ向けて力強く表現されてきました。一方、日本の絵画では、言葉や大げさな身振りよりも、沈黙や距離感、視線のそらし方といった控えめな表現を通じて、相手に「気づかせる」ことが重視されてきました。つまり、西洋は「感じたことを伝える文化」、日本は「感じ取ってもらう文化」と言えるでしょう。こうした違いは、ボディランゲージの役割そのものにまで及んでいます。
多くの作品を比較して見えてくるのは、身体には時代や地域を超えて「語る力」が備わっているということです。しかし、その語り方は文化によってまったく異なります。たとえば、日本画では、沈黙や余白、象徴的なモチーフが感情を伝える手段として機能します。言葉を使わずとも、静けさの中に深い情感をたたえた作品が少なくありません。対して西洋画では、手を高く掲げる、口を大きく開く、身体を激しくひねるといったダイナミックな身振りによって、感情が見る者に直接伝わるよう構成されています。
いずれも「身体は語る」という点では共通していますが、「何を、どのように語るか」は、文化背景によって大きく異なるのです。
今回のテーマでは、日本画と西洋画という対照的な視点から、非言語表現のあり方を読み解いてきました。こうした比較を通じて、私たちは日々の自分自身の姿勢や目線の動きにも、あらためて意識を向けるようになるはずです。また、他者の沈黙、わずかな視線の動き、指先の揺れや肩の傾きといった、ささやかなサインにも自然と目が向くようになるでしょう。そうした微細な表現にこそ、心の奥底にある本音や感情がにじみ出ているのです。
それを丁寧に読み取る力は、異文化理解にとどまらず、あらゆる人間関係において重要な役割を果たすはずです。
















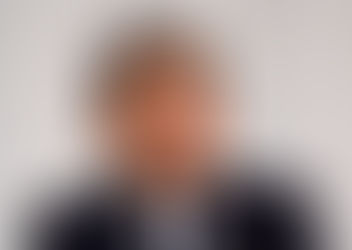














Comments